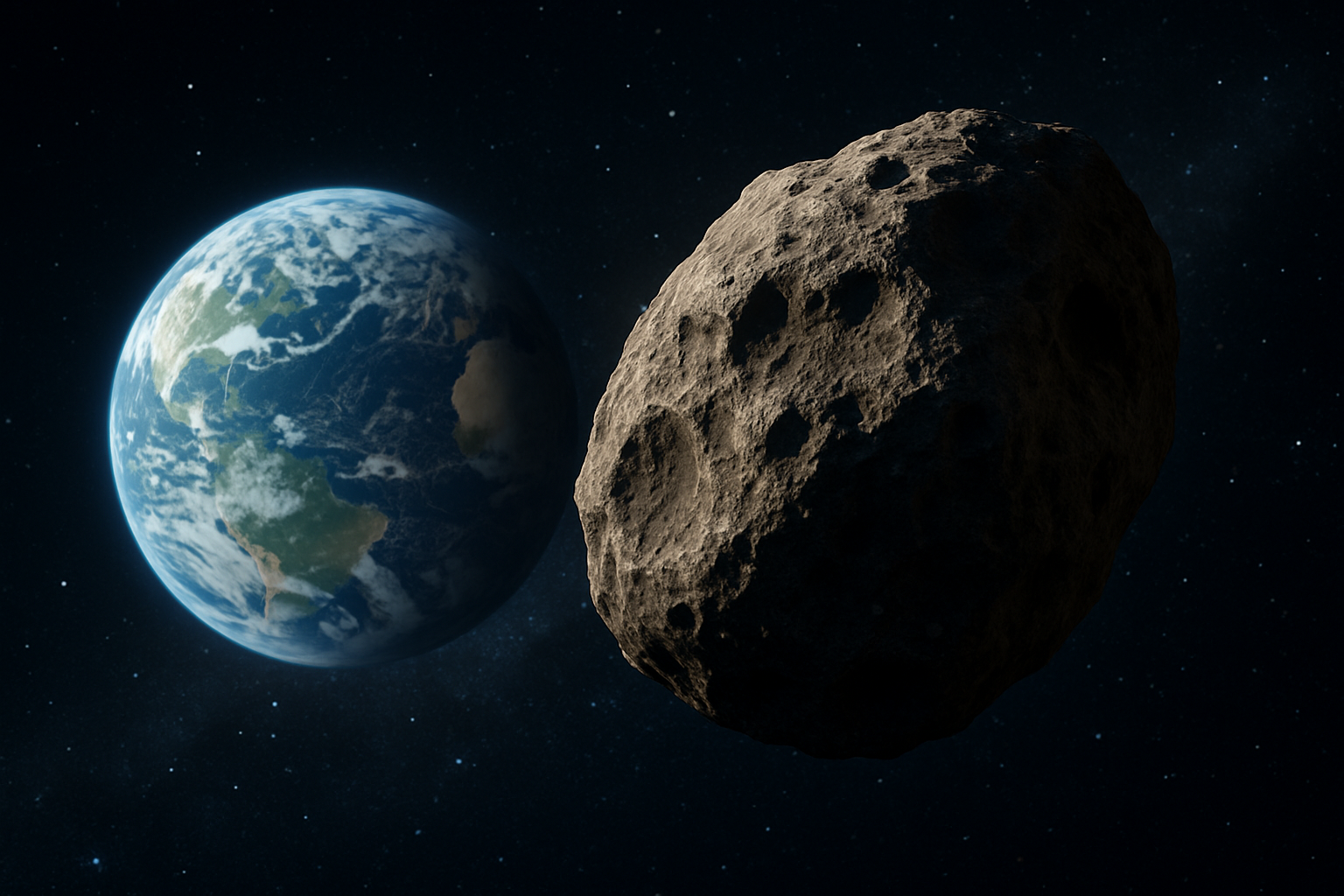
小惑星衝突リスクの評価と対策分析
小惑星衝突リスクの評価と対策分析
直径40~90メートル程度の小惑星が約7年後に地球へ衝突する可能性が1.9%と予測される状況について、想定被害の規模と必要な対策を以下に分析します。
期待金額(被害予測額)の算出
被害の想定: 直径50m前後の小惑星が地球に衝突した場合、そのエネルギーは数メガトン級のTNT火薬に相当します。1908年のツングースカ事件では、直径約50mの天体が大気中で爆発し、TNT火薬10~50メガトンに匹敵する威力で約2,000平方キロメートルの森(約8,000万本の樹木)をなぎ倒しました 。幸い極僻地での空中爆発だったため人的被害はほとんどありませんでしたが、人口密集地で同規模の爆発が起これば都市一つが壊滅し甚大な被害が生じると考えられます。   近年では2013年にロシア上空で約20mの隕石が爆発し、約400~500キロトン相当のエネルギーで衝撃波を発生させ、負傷者約1,500人・建物被害7,200棟以上を記録しました 。この事例(チェリャビンスク隕石)でも爆発は上空で起こり地表への直接被害は限定的でしたが、それでも被害総額3,300万ドル以上(約40億円)と見積もられています 。
期待損害額の推定: 小惑星の落下地点によって被害は大きく変動します。人的被害は、人口密集地への直撃なら数万~数百万人の死傷もありえますが、海洋や過疎地であれば比較的少なく抑えられる可能性があります。経済的損害も、都市インフラ(建築物、交通網、電力・通信など)が破壊されれば数兆円規模(数十億ドル規模)の損失となり得ます。一方、人里離れた地域や海上であれば直接的な物的損害は限定的ですが、海洋衝突時は津波被害が沿岸部に及ぶリスクも考慮すべきです。これらシナリオを平均した被害額を仮に数千億~1兆円程度と見積もると、衝突確率1.9%を乗じた期待損害額は数十億円から数百億円規模になります。例えば、平均的な被害シナリオを5,000億円(約50億ドル)と仮定すれば期待値は約95億円(約0.95億ドル)となります。これは無視できないリスクコストであり、被害の不確実性や社会的影響(恐怖や混乱の波及)を踏まえれば、実際のリスク評価ではこの期待値以上に深刻に受け止めるべきでしょう。
軌道変更プロジェクトの技術的実現可能性
既存の回避技術: 幸い、小惑星の軌道を変えるための技術は近年発展してきています。主な方法として以下が研究・検証されています。 • 運動エネルギー衝突(キネティック・インパクター): 宇宙機を小惑星に体当たりさせ、その運動量で軌道をわずかに変える方法です。NASAは2022年に「DART」ミッションでこの手法を実証し、小惑星(約160mの衛星天体)の軌道周期を32分短縮することに成功しました 。この実験成功により、「危険な小惑星が出現した際には運動衝突で軌道変更が可能」であることが示されています 。直径40~90m級の天体であれば、この方法で数ミリ毎秒程度の速度変化を与えるだけで地球衝突コースから逸脱させられる可能性が高いと考えられます。 • 核爆発による偏向: 核弾頭を用いて小惑星を爆破または爆風で押し出す方法です。核の直接爆砕で小惑星を粉々にすると破片が地球に降り注ぐ恐れがあるため、現実的には小惑星近傍での核爆発の衝撃波で軌道を変えることを狙います 。核兵器は極めて強力なエネルギーを与えられるため短期間で大きな軌道変更が可能と期待されますが、宇宙空間での核使用には技術的・法的ハードルが非常に高く(宇宙条約や核実験禁止条約との抵触)、実際に試行された前例もありません。 • 重力トラクター: 小惑星のそばに宇宙船を飛行させ、その微弱な重力で小惑星を徐々に引っ張る方法です。推進装置でゆっくりと機体位置を維持しつつ、数年〜数十年かけて軌道をずらすもので、極めて精密な制御が可能である利点があります。  実現には長い準備期間が必要ですが、人類はすでに探査機の小惑星ランデブーやサンプルリターン(NASAのオシリス・レックス探査機やJAXAのはやぶさミッションなど)に成功しており、この手法に必要な誘導・制御技術基盤は存在します 。
実現可能性の評価: 上記のうち、運動エネルギー衝突は現時点で最も現実的で実績のある手法です 。7年のリードタイムがある場合、早期に計画を立ち上げれば打上げ~衝突まで数年の余裕を持って軌道変更を試みることができます。DARTの成功例からすると、類似のミッションを実施する技術的ハードルはそれほど高くなく、目標天体に命中させる精度も達成済みです 。仮に最初の衝突で軌道変更量が不十分でも、追加の宇宙機を打ち上げて再衝突させる計画を立てることで成功確率を高められます。核オプションは最後の手段ですが、リードタイムが極端に短い場合や運動衝突では効果不足のケースに備えて研究が進められています。ただし核兵器を宇宙で使用することへの国際的合意形成や安全管理の問題があるため、現状では現実的な選択肢は非核の運動エネルギー方式になるでしょう。総合的に見て、現在の技術水準において直径50m級の小惑星の軌道変更は実現可能であり、成功の見込みも十分にあります。  重要なのは速やかにプロジェクトを開始し、複数の対策オプションを検討・併行準備することでリスクヘッジすることです。
対策費の概算
ミッション規模と必要経費: 直径40~90m級の小惑星への対策としては、上記の運動エネルギー衝突ミッションを軸に検討します。必要な費用は、宇宙機の開発・製造、打ち上げロケット、運用コストなどからなります。参考までに、NASAが2022年に実施したDARTミッション(小惑星への体当たり実験)には、約3億3千万ドル(約360億円)の予算が投じられました 。この金額には宇宙機本体の開発費・打上げ費用・運用費が含まれています。今回のケースでも、同程度規模のインパクタ宇宙機を1~2機打ち上げる計画であれば数億ドル(数百億円)規模の予算が必要と見積もられます。
追加要素による増減: 仮に核爆破案を採用する場合、宇宙用の特殊な核装置の開発や安全対策に追加コストがかかる可能性があります。また複数のバックアップミッションを並行準備する場合も費用は増大します。しかし全体予算が数十億ドル(数千億円)を超える可能性は低いと考えられます。  実際、米国の宇宙財団B612の関係者であるシュウェイカート氏は「小惑星偏向ミッションは概ね50億~100億ドル以内(約500億~1,000億円程度)で実行可能で、決して実現不可能な額ではない」と試算しています 。これは各国が協力し費用を分担すれば十分賄える水準であり、現実的な予算感といえます。なお、事前調査(小惑星の性質や軌道の詳細測定)や万一の失敗時に備えた予備機開発などを含め、ある程度の予備費も見込んで計画を立案する必要があります。
費用対効果の評価
期待損失 vs 対策費: 上記で算出した期待被害額(数十億~数百億円規模)と、対策に要する費用(数百億円規模)を比較すると、両者は概ね同程度のオーダーになる可能性があります。一見すると「1.9%のリスクに数百億円を投じる」ことは費用対効果が釣り合わないようにも思えます。しかし、期待値計算には表れないリスクの偏り(低頻度だが壊滅的被害)を考慮すれば、費用対効果はむしろ十分に高いと評価できます。仮に対策を講じなかった場合、1.9%という無視できない確率で都市壊滅レベルの災害が発生しうるのです。その被害は人的損失・経済損失ともに甚大で、社会に与える打撃や混乱の波及効果は計り知れません。一方で、対策プロジェクトに投資することでその最悪シナリオをほぼ確実に回避できるのであれば、支出に見合うリターン(災害回避効果)は極めて大きいと言えます。
社会的・経済的観点: また費用対効果を評価する際には、純粋な金銭換算だけでなく社会的価値も考慮する必要があります。人命救助や文明の保全といった価値は金銭には代えられず、「起こり得る最悪の事態を防ぐ」という保険的投資は公共政策上正当化されます。実際、宇宙規模の脅威に対処することは国家や国際社会の責務であり、たとえリスク発生確率が低くとも対応策を講じておく意義は大きいとされています 。今回のケースでも、1.9%という決して無視できない確率が提示されている以上、早期に軌道変更プロジェクトを開始しリスク低減を図ることが社会的に求められるでしょう。費用面でも、参加各国で国際協力して費用負担を分散すれば一国あたりの負担は軽減できます 。加えて、本プロジェクトの遂行により得られる技術・知見は将来の惑星防衛能力向上につながり、長期的な安全保障投資とも位置付けられます。
総合判断: 以上を踏まえると、軌道変更プロジェクトは費用対効果に優れると考えられます。期待損害額と対策費用が同程度であったとしても、未然に災害を防げる意義は計り知れません。むしろ、わずか数百億円~数千億円の投入で地球規模の大惨事を回避できるのであれば安いものです。よって現段階で直ちにプロジェクトを立ち上げ、関係各所(宇宙機関、政府、防衛当局など)が連携して具体的なミッション計画策定に着手すべきでしょう。
参考資料: • 【5】 CNN報道経由: Paul Chodas(NASA/CNEOS)コメント「サイズが大きい場合、衝突の爆風被害は衝突地点から半径50kmにも及ぶ可能性がある」  • 【16】 ブリタニカ百科事典: 「ツングースカ事件」の概要(2000平方kmの森林が倒壊、エネルギーは最大15メガトン)   • 【26】 ロイター通信: 「2013年チェリャビンスク隕石」による被害報告(負傷者約1,200人、被害額3,300万ドル)  • 【27】 Arms Control Association: Michael Krepon “Planetary Defense: The Nuclear Option Against Asteroids” – 過去の隕石衝突事例(ツングースカ・チェリャビンスク)とDARTミッションの成果    • 【21】 Wikipedia: DARTミッション(小惑星ディディモス衛星への衝突で軌道周期を32分短縮)  • 【24】 Space.com: Asteroid Deflectionに関する記事(人類が持つ技術オプションと費用見積に関する専門家コメント)   • 【31】 NASA: DARTミッションによる小惑星軌道偏向技術の実証についての記述  • 【30】 Arms Control Association: 宇宙における核爆発による偏向手法と法的課題  • 【7】 ResearchGate経由: 小惑星偏向手法の比較研究(運動エネルギー方式は数百メートル以下のNEOに最も実現可能)